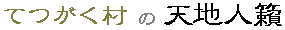☆ 2016-03-02(水) ☆ 講と総有
§0.分家する息子は講に入れて、結婚した娘は入れないなんて不合理じゃない?§1.講山売却の分配をめぐる問題§2.共有と総有§3.総有と前近...
§0.分家する息子は講に入れて、結婚した娘は入れないなんて不合理じゃない?
§1.講山売却の分配をめぐる問題
§2.共有と総有
§3.総有と前近代的な生活
§4.総有意識の攪乱と希薄化
§5.慣習法的に認知される総有
----------------------------------------------------
§1. 講山売却金の分配をめぐる問題
§2.共有と総有
公有の祖型としての総有
§3.総有と前近代的な生活
全体として、地縁によって結合されている生活
流動性に乏しい地縁関係
相互扶助における、共同性の優位
現地での利用
§4.総有意識の攪乱と希薄化
所有関係の近代化
生活の近代化
§5.慣習法的に認知される総有
----------------------------------------------------
講中 2002-04-19
§1.講山売却の分配をめぐる問題
§2.共有と総有
§3.総有と前近代的な生活
§4.総有意識の攪乱と希薄化
§5.慣習法的に認知される総有
----------------------------------------------------
先日、講の役員会があった。その時の議題のひとつに講規約の一部改正があった。
講 : 信仰を同じくする地縁集団。(集団内には血縁関係もある。)生活上の相互扶助、主として葬儀での相互扶助、を目的とする。§0.分家する息子は講に入れて、結婚した娘は入れないなんて不合理じゃない?
講中は同じ寺の門徒である。それゆえ、寺の下部組織のような機能もある。
講の規約を見ながら、或る男性が疑問を呈した。
講員の資格を規定する条項は次のようになっている。
「講への新規加入は、講員全員の賛成を要する。ただし、講員死亡の場合、その主たる相続人は無条件に加入を認めるものとする。」
「講への新規加入は、講員全員の賛成を要する。ただし、講員死亡の場合、その主たる相続人は無条件に加入を認めるものとする。」
条項には明記されていないが、講の慣習として、分家(この地では「でえ」と呼ぶ)の場合も無条件に加入を認められる。ただし、講組織が存在する地区ないしその近隣で分家し、講の活動に参加できるという条件がある。
さて、その人の疑問は、結婚して出ていった娘についてだった。他家に嫁いだ娘が講に加入できないのは、おかしいじゃないか、と彼は言う。
「息子(この場合、《跡取り息子》や分家した息子をいう)が講に加入できて、娘ができない、というのは、男女差別だ。また、講には財産(不動産、および預金)があるが、講に加入できないなら、親は講の財産の共有者なのに、娘が親のその遺産を相続できないことになる。」
このように彼は疑問を説明した。
(婿をとる《跡取り娘》の場合は、跡取り息子と同等の扱い。)
「息子(この場合、《跡取り息子》や分家した息子をいう)が講に加入できて、娘ができない、というのは、男女差別だ。また、講には財産(不動産、および預金)があるが、講に加入できないなら、親は講の財産の共有者なのに、娘が親のその遺産を相続できないことになる。」
このように彼は疑問を説明した。
(婿をとる《跡取り娘》の場合は、跡取り息子と同等の扱い。)
しばらく意見のやりとりがあったあと、その疑問に対して、或る女性が「今どき講に入りたいゆう人はおらんよ。そんなことがあればええんじゃけどね」と笑いながら対応をした。舌鋒をかわされた男性もやはり笑いながら、現実味のない事例をあげつらっても詮ないと判断したのか、それ以上の議論をやめた。
実際、近年は、講の構成員であっても、葬儀のさい、講中の手を煩わすのを嫌い、私営の葬祭施設を利用するようになった。そうすれば、講中の仕事は、帳場だけになるからである。(以前は、自宅ないし自治会館[かつては「説教場」と呼ばれ、村の共同施設だったが、市からの補助金を受けて「自治会館」と名称変更した]を利用していたので、会場の準備、帳場、まかないなど、葬儀の全段階で講中の手がどうしても必要だった。)規約は、講の目的として、「講員の親善と相互扶助」をうたっているが、相互扶助は避けられる傾向にあるのが現状である。ましてや、人間関係が煩わしくなるのをわざわざ求めて、講に加入してくることは考えられない。
§1. 講山売却金の分配をめぐる問題
しかし、私の頭には、彼の問題提起が残った。講組織は近代以前から存在しているので、前近代的な性格を残している。彼の問題提起には、その性格のうちの所有関係が絡んでいて、それが私の思索を刺激した。
近代的な所有関係からすると、講の財産は講員の 共 有 のようにみえる。15年余り前、講所有の山(講山)が市によって買収された。売却金は、講としては、講の基金として預金することにした。ところが、売却金の分配をめぐって問題が生じたのである。
その基金を享受するのは、慣習的には、講の、現在の、構成員である。そして、かつては講に所属していたが、いまは講のある地域から出て行き、講の活動とは関わりのなくなった家族、およびその末裔、つまり講からの脱退者は、享受者からは除外される。
しかし、近代的な所有関係の見地からは、組織を脱退しても、脱退以前に、自分ないし先祖が、講山の共有者として登記されていれば、講山に対する相応の所有権はあり、したがって、講山売却金に対する権利もある。推測だが、遅くとも明治の地租改正時(明治6年、1873年)までに(*)、講山は当時の講員たち(おそらくは、全員)の名義で所有された。
(*)明治の地租改正を指標時点にしたのは次のような理由によってである。
地租改正時に、民有地と官有地の区別がなされ、民有地に地租が課せられた。そして、民有地で所有者が特定できないところは、官有化された。入会地や用水路は村全体とか水利権者全体で所有されていて、所有者が特定できない場合があったので、官有化されたものも少なからずあった。たとえば、現在、法定外公共物に分類されている用水路は、そのような歴史をもっている。
ところが、講山は民有地のままである。したがって、遅くとも地租改正までに-地租改正をきっかけとして?-、特定の所有者たちによる共有地になっていたはずである。
売却時の講役員たちは、講山の共有名義人ないしその子孫で、講の所在地には在住せず(外国在住の人もいたようである)、かつ講の活動と関わりがなくなった人たちと、連絡をとり、講財産の慣習的なありようを説明して、売却金に対する権利放棄を要請した。しかし、権利を主張して譲らない人もいた。隣町の講での先例からすれば、裁判にもちこめば講側が勝てる、との話もあった。しかし、裁判に必要な費用や日数を考慮し、また、仮に売却金を分割するとしても大金にはならないと判断して、権利を主張する人には、相応の額を分配することにした。
売却金分配問題は落着したが、私には、裁判をすれば勝てる、ということが引っかかっていた。共有者であれば、またその子孫であれば、共有している財産への権利があるはずなのに、なぜ、その権利を否定する講が勝てるのだろうか。その疑問が、私には合理的には納得できずに残った。
§2.共有と総有
ところが、井手[農業用水路]の水利権をめぐる議論のなかで、その理由がみえてきた。(井手の水利権をめぐる議論-数年にわたったが-は、井手の水利権者-私もその一人-と、井手の財産管理権をもつ市との間で、たたかわされた。この件に関しては、いずれ記事にすることがあるかもしれない。)
明治以前、入会地や用水路は、民有である場合には、所有形態は、それらに関係する人たちの 共 有 ではなく、 総 有 であった。土地を共有している場合、共有者は、その土地に対する相応の所有権がある。したがって、相応分の分割を請求できる。上の例でいえば、講山の売却金の配分を請求できることになる。ところが総有の場合、個々人は、土地の利用(入会地の草を刈り木を伐ったり、用水路の水を田んぼに引水する)はできるが、土地(財産)の分割は請求できない。言い換えれば、個々人には土地の所有権は、部分的であれ、ない。では、だれが土地所有者であるかと言えば、全体としての、入会地利用者集団や水利権者集団である。言ってみれば、ひとつの《組織》である。組織の構成員は出入りがありうる。そして、脱退した構成員は土地をもって出ることはできないのである。土地に対する利用権を放棄すれば、組織に属する限りでもっていた、土地に対する所有権も失う。土地は、完全な形で、《組織》に所属することをやめないのである。
講山は、そしてその売却金は、いま述べたような、総有的に所有されてきた財産である。
公有の祖型としての総有
余談に逸れると、総有は、公有の祖型と考えることができるかもしれない。公有されていて、生活に必要な財産、たとえば道路とか公民館とかは、公共団体に属する人間(「市民」と呼ぶことにしよう)なら、だれでも利用できる。また、その財産は、市民の税金で購入され維持されている。しかし、市民は財産の分割は請求できない。市民には利用権はあっても、所有権はないのである。かりに、たとえば市民をやめた時には財産の分割が可能だとすれば、道路が分断されたり公民館の一部の施設が利用できなくなったりして、利用に支障が生じることになろう。
公共物と市民との間には、財産所有と財産享受との関係に断絶がある。市民は公共物を享受することができるが、その財産管理は公共団体だからである。そして、その関係が一体化したのが、講の構成員と講山の関係であろう。講員は、個人として、財産の享受者であり、同時に、集団として、財産の管理者だからである。
ただ、総有の場合、所有権は組織に属する、といっても、その組織は、法人のように、実際の構成員とは独立したものとして意識されていたわけではない。そもそも法人のような観念はなかった。言い換えれば、講という組織は現構成員全体と等しい。最前は組織という言葉を使って説明したが、その言葉は現構成員全体の単なる名称以外の意味はもたない。
| 「公有」物 | 「総有」物 |
| 財産所有:公共団体 利用者:市民 | 財産所有:組織=構成員全体 利用者:構成員 |
最初に紹介したエピソードに戻ろう。講山は総有的に所有されていることからして、嫁いだ娘には、講山に対する権利がないのは当然である。結婚した娘は、同じ講に属する家に嫁ぐ場合を除き、もはや講の構成員ではなくなるのであり、したがって、講の山に対する、いかなる意味での、所有権も失うのである。
§3.総有と前近代的な生活
さて、今まで説明してきた総有的所有は、どういう意味で前近代的のだろうか。講員たちの生活との関係で、考えてみよう。
全体として、地縁によって結合されている生活
冒頭に注釈したように、講は、構成員の間に血縁関係が目立ちはするが、基本的には地縁集団である。さらに、地縁は、たまたま住居が近隣であると、いう空間的隣接の意味だけでの関係(たとえば、団地の地縁関係ははこのような意味での関係であろう)ではなく、生業がその土地に根ざしている、という意味での関係でもある。具体的に言えば、構成員は農業という生業を通して地縁を結んでいる。生産空間(農地)が土地と不可分離に一体化し、また生産手段の一部(たとえば水路)を共同利用または相互融通している。つまり、生活全体が地縁によって有機的に結合されているのが、講の人間関係の基盤である。そして、このような関係は、近代の産業革命以前に特徴的な関係であろう。
流動性に乏しい地縁関係
その人間関係は家族単位でみた場合、流動性に乏しい。農業は職住隣接が必要条件である生業なので、農家は住居を、農地から遠く離れた場所に移すことはできない。子供は跡取り以外は、分家できなければ、他郷に出ていく。つまり、家族の構成員レヴェルで見れば、当然、流動性はあるが、家族のレヴェルでみれば、流動性に乏しいのである。
相互扶助における、共同性の優位
葬儀は人手と財力を必要とする。その人手と財力は家族だけでは賄いがたい負担であった。その負担を互助組織(講)がになう。講山は、棺作りや火葬のための木材を供給する。講小屋におさめられている什器類は大人数の煮炊きのためである。会場の準備、煮炊き、葬式、野辺の送り、火葬を講中が手伝う。葬儀は、一人でも、家族だけでも、できることを、他人たちがやってきて助けてくれる、といった仕事ではない。そうではなく、他人たちの力を借りてはじめてなりたつような儀式である。言い換えれば、葬儀という個人性に、講中という他の複数の個人性が加算される相互扶助ではなく、講中という共同性に支えられてはじめて個人性が可能になるような相互扶助である。つまり、講中の活動には、共同性あるいは相互個人性の優位があった。
現地での利用
さらに、講の財産は、現在の土地に生活していてはじめて有益な利用ができる。現代のような交通手段のない時代には、隣村に移住しただけで、すでに利用が無意味になる。したがって、講を脱退すると、講八分にあった結果でないのであれば、余所に居を移した結果であるので、講の財産に対する利用権を要求する意味がない。財産は、特定の用途と結びつく限りにおいて所有されていると観念されているとすれば、所有権を要求する意味もまたなくなる。
総有という所有形態は、上のような前近代的な生活に根ざした所有形態である、と言えよう。
§4.総有意識の攪乱と希薄化
ところが、総有の意識は近代化とともに薄れていく。
所有関係の近代化
ひとつは、明治の地租改正時に講の財産が共同名義で登記された結果、講財産は、慣習的に実際上、総有でありながらも、法律的には、共有としての仮象をとったのが原因であろう。旧民法によれば、家督の継承者が親の財産の相続者である。すると、もし講山が共有であれば、「講員死亡の場合、その主たる相続人は無条件に加入を認める」のは当然であるにせよ、親の財産を相続する権利をもたない分家も無条件に講に加入できるということは法律的には不合理である。しかし他方、講の慣習として、分家の無条件の講加入は認められている。その点からすると、総有の事実は変わらずにある。それに、少なくとも第2次世界大戦終了までは、§3で述べた、総有の意識の基盤となる前近代的な生活は、続いていた。それにもかかわらず、明示される法律上の共有が、暗黙の事実慣習上の総有を、講関係者の目から、覆い隠す可能性はあっただろう。
戦後の民法改正は、総有の観念をさらに攪乱することになったと思われる。改正民法では、子供全員に平等な相続権を認めている。一人の特定の子供(旧民法によれば、家督相続者)がすべて相続するわけではない。したがって、講財産が共有の仮象をとった上で、改正民法の相続規定が加われば、財産権は、講の活動と無関係になった者にまで及ぶ、という観念が可能になる。他郷に住んで講の活動と無縁になり、また講の基盤となる農村の生活は実感し得ないような人にあっては、そのような観念が確固とした信念になっても不思議はない。
生活の近代化
それに、講中内部においても、生活様式が変わり、それとともに、総有的所有が生活実感からかけ離れた奇妙なものに思えてくる。支えあいながら講の活動をやっていた時代とは比較にならないくらい物質的に豊かになった現代では、私営の施設を借り、講中の手を煩わせずに葬儀をおこなうことができるだけの財力はある。また、生業も農業が中心ではなり、個人意識が強くなる。
§5.慣習法的に認知される総有
このような状況で講山の売却がなされたのである。しかし、総有という前近代的な所有関係は、実際には、近代的に変形されたわけではない。法律的に否定されたわけでもない。法律の門外漢の考えではあるが、総有は慣習法的に認知されており、それがゆえ、売却金を講の基本金としようとする講が、売却金の分配を要求する講外の人と裁判すると、勝ちうるのである。
講山の売却金は、現在では講の名義で保有されている。個人に分配するのではなく、総有的に所有されている財産として保有されている。そのような手続のために、講山売却金配分問題をきっかけに、講の慣習が講規約として明文化された。そのことによって、講は法律的には法人ではないが、法人扱いをされる根拠ができたのはないだろか。ただ、講中が一致して講財産を総有的なものとして認識しているわけではないように、私には思える。
----------------------------------------------------
講について、別の観点から記事を書いたことがあります。興味のある方は、ご覧ください。
講中 2002-04-19