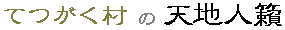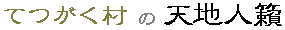☆
2003-02-03 ☆
寒肥
□ (旧暦 1
月3
日)
−寒の内;−野菜にも寒肥;−自然農法の「施肥」;−春を気長に待つ寒肥
寒の内 −1月6日(小寒)から2月2日(節分)まで−
□二十四節気で言えば、小寒(1月6日)の寒の入りから、大寒(1月20日)を経て、立春(2月3日)の寒の明けまでの約1カ月は、一年で一番寒い時期である。実際、統計上も、気温がもっとも低い時期になっている。広島あたりでは、この時期にあわせたように気温のグラフが谷底を描いている。
□新暦では寒は1月と重なるので、「春」と言えなくもないのだが、実感にはほど遠い。それでも、晴れた日には、冬至以来しだいに長く高くなってきている日差しに、春のかすかな気配を感じることもある。しかも、この時期になると、なぜか目白を目撃することが多くなる。実家の隣にあまり日の当たらぬ木立がある。梅、棕櫚、柚子、ぐみ、柿などいろいろな木が植わっている。そこに目白がやって来るのである。萌葱色というのだろうか、目白の羽の色は、わたしの頭の中ではすぐに梅の花に結びいて、春の象徴になっている。
□しかし、そんな注意を働かせなければ、この時期はやはり厳寒である。今年の冬は、暖冬予報に反して、11月に入るととたんに寒くなり、それ以降は全般に低温が続いた。1月29日夜から28日にかけては、広島あたりでは珍しい大雪になった。今年の冬は久しぶりに本来の冬に戻ったようである。
□真冬には、畑の作物のほとんどは寒さに耐えて活動を止めているように見える。ブロッコリーとか紅菜薹(薹の立った茎を食べる中国野菜)は、花蕾を太らせたり花をつけたりしているが、エンドウやソラマメは数枚の葉をつけたまま成長がとまっている。タマネギも葉先が枯れこそすれ、葉は伸びないし、ましてや葉数は増えない。真冬にも成長を続ける野菜は少ない。大半は冬眠状態である。
野菜にも寒肥
□寒肥という言葉がある。寒の時期、春以降の成長のため、庭木に施す肥料をいうのが本来の意味のようである。この時期、根はまだ活動を開始していない。だから、施肥のため木の周辺を掘り返し、根を切ったとしても、あまり影響がない。樹木も眠っているのである。木を伐採するのは寒がいい、と言われている。活動期のようには水分を含まず、木質がしっかりしているからであろう。(ちなみに、竹は11月に伐るのがいい、と聞いたことがある。)
□しかし、野菜にも寒肥をやる。わたしは農耕をやり始めたころは、寒肥の観念はもっていなかった。栽培のノウハウ本に書いてある通りに、肥料をやっていただけである。ところが、最初の年の春か、隣のおばあさんが「あんたぁ、エンドウ
[村では「空豆」のこと]に肥をやっちょったじゃろう」とわたしに話しかけた。わたしはたしかに春になって追い肥をやった。白色で粒状の化学肥料なので土の表面では目立ちやすい。「エンドウは、いまやったら、茎がやおうなって
[軟らかくなって]アブラムシがつく。寒にやらんにゃわからん
[だめだ]。」空豆はアブラムシがつきやすい。ひどいときには、そのせいで成長がとまってしまう。春に肥料をやると、すでに活動を開始している野菜は旺盛に吸収して大きくなる。虫は肥料をたっぷりと吸い込んだ野菜につきやすいのである。
□またこんなこともあった。
アーティチョーク[蕾を食用にする、欧州原産の大アザミ。日本名は、なぜかチョウセンアザミ。]を種から育てて苗を作った。苗が余ったので、隣家に分けた。息子家族が海外赴任中にアーティチョークを知り、子どもなどは大好きだ、というのを聞いていたからである。アーティチョークは春に種を蒔き、秋に定植する。収穫は翌年の初夏からである。次の年、我が家のアーティチョークは雑草とともに放っておいたところ、あまり大きくならなかった。ところが、隣家の畑ではアーティチョークが大きな蕾をつけた。
□「本家はこまい
[小さい]のに、分家がおおけぇなって、すまんの」と隣の主人は笑って言った。その人の家の分家が、隣のおばあさんの家である。おばあさんは本家の畑の一部を耕作している。だから、おばあさんは秘密を明かすようにわたしに教えてくれた。「寒にしっかり肥をやったけんのぉ。」
自然農法の「施肥」
□そんな話を聞いても、慣行農法でやっていた時期は、寒肥には注意を払わなかった。マニュアル通りの施肥で野菜はできたからである。
□ところが、去年春から自然農法畝を、耕作面積の半分くらいまで拡大した。自然畝では、土が長い間化学肥料で痛めつけられていたせいか(農薬は、わたしが農耕をやり始めてから現在までの8年間、畑では一度も使ったことはない)、したがって、自然農法に適した土壌環境と植生(すなわち、多様な雑草が繁茂すること)へと熟していないためか、貧弱な野菜しかできない。そこで、不耕起、不施肥、不除草の原則のうち、不施肥原則を曲げて、金肥としては発酵鶏糞、自家供給の肥料としては米糠(そのまま施したり、発酵させて施したりする)と台所残さを施している。
□しかし、慣行農法で化学肥料を施す場合とは違い、狙った時に肥料をきかす、という細かいコントロールができない。発酵鶏糞は化学肥料並の即効性がありはする。しかし、自然農法と慣行農法とでは、ききかたに違いがでてしまう。慣行農法の場合は、施肥のあと、鍬で中打ち[中耕]して肥料と土を混ぜるため、肥料のききが速い。ところが、自然農法では、畝の表面に施肥するだけである。鍬で掘り返すのは、不耕起原則に反するし、たとえ鍬も使おうとしても、草が絡まり、草の根が邪魔をする。だから、雨が降らなければ、肥料は土中に浸透しない。雨が降ったとしても、土と混ぜられた肥料ほどにはしっかりと浸透しない。自然農法での施肥は、きくまで気長に待たなければならないのである。だから、慣行農法の施肥マニュアルはそのままでは通用しない。
□そんな自然農法の現状を考えていると、寒肥が現実味を帯びて思い浮かんできた。厳寒期に施肥してやる。根の動きだすのは、おそらく3月始めだろうから、1月余り待ち時間がある。するとその間に、雪や雨で肥料が土中にゆっくりと浸透する。根が目覚めると、まわりで熟成した肥料が待っている。野菜はそれを吸収しながら、春の伸長の足固めをする。冬から春にかけての、緩慢な肥料の分解とゆっくりとした作物の成長とに応じた施肥として、寒肥が思い浮かんだのである。
□春からの成長が収穫につながる作物は、わが家の畑で言えば、空豆やエンドウの豆類、ニンニク、アーティチョーク、タマネギ、高菜(漬け物用)などである。タマネギと高菜は慣行畝に植わっているので、化学肥料を施した。(タマネギは、寒肥という観念なしに、いままで、12月終わり/1月始めと1月終わり/2月始めの2回、追肥してきた。タマネギは、2月半ば以降に追肥すると病気になりやすい。)豆類にしてもニンニクにしても、肥料が少なくても大きくなる。豆類の場合は、根粒菌が窒素を固定する。ニンニクの場合は、年数の浅い自然畝で作っても、そこそこの大きさになる。理由は分からないが、他のユリ科の野菜(ニラ、ラッキョウ、アサツキ、ネギなど)同様、悪条件に強い、という印象はある。そんな質の野菜ではあるが、ゆっくりと土中に浸透して根の目覚めを待つ、という寒肥の、いかにも「自然な」イメージが面白く、また、むろん収量を上げたいという欲にもかられて、アーティチョークに加えて、豆類とニンニクにも発酵鶏糞を施した。
春を気長に待つ寒肥
□想像をたくましくすれば、化学肥料に頼る農法以前は、畑作でも、観念として意識されていたかどうかは別として、寒肥が施されていたのではないだろうか。化学肥料利用の歴史はそう長くない。日本の近代化が徹底され始める1960年以前は、下肥や厩肥が主体であった。有機肥料は、化学肥料のように取り扱いが簡単で、しかも効き目がよい、というわけではない(「効き目がよい」でいいたいのは、少量でも強く即効的なききかたをする、ということである)。効率がよくない、とでも表現できようか。その有機肥料だけがたよりの農耕であれば、季節にかかわらず、狙いすましたように適期に即座にきかせる施肥はできない。寒暖や乾湿の変化を見通しながら、息の長い施肥をしなければならない。
□90を過ぎている隣のおばあさんは、農耕生活の最初の半分を有機肥料のみでやってきたはずである。おばあさんにとって、だから、寒肥とは冬のさなかに春を思いやる、習性となった生きかたといえよう。おばあさんは、自然農法などは知らない。きちんと砕土し、整地する。草は生やさない。肥料もしっかりやる。しかし、不耕起、不除草、不施肥などと農法の原則を述べたてるわたしよりはるか前から、「自然農法」を生きてきたのである。