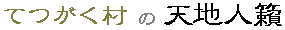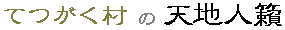��
2003-01-22 ���@
�Ƃ�ǁA����̉Ղ�
�� �i���� 12
��20
���j
�|�u������������o�Ă�I�v�G�|�����̖�̉Ղ��G�|����i���z���A��j�Ɣ_�k
��1��12��(��)�͂Ƃ�ǂ������B�Ƃ�ǂ͏������̍s���ł��邪�A���ł�15���ɋ߂��T���ɍs����B���N��13��(�y)�������B
�����N�́A�킽���̓�����Ƃ�����Ă��邱�ƂɂȂ����B�����ɂ́A�킽���̑��q�Ɠ����N�̏��̎q������B�L���s���ɏZ��ł���̂ŁA�q�ǂ������R�ɐG���@����Ȃ��A���Ɉ�x���炢�A�F�숢�˂ɂ���s���_���̃C�x���g�ɎQ�����Ă���A�Ƃ����̂��āA�Ƃ�ǂɗU�����B�����Ƃ킽���̋��ʂ̗F�l�ł��鏗�����A�����ɂ��Ă���Ă����B
���Ƃ�ǂ̏�����12������n�܂�B12�����ɁA�܂��A�R����X�X�L��G���o���Ă���B�����āA�N�������āA�Ƃ�ǂ�1�T�ԂقǑO�ɁA�m����������āA�Ƃ�ǂ��܂��i�|�ō��g�݂�����A�X�X�L��m�œ��t�����ĂƂ�ǂ�g�ݗ��Ă邱�Ƃ��A�u�Ƃ�ǂ��܂��v�ƌ����B�Ȃ��A�Ƃ�ǂ̎ʐ^���������N���b�N���Ă��������B�j�B
���킪�Ƃł́A���N����́A���Ƃ̂���n��ł͂Ȃ��A�����̉��~�Ɠc��������n��ŁA�Ƃ�ǂɎQ�������Ă�����Ă��邪�A���̒n��͎�����̔ǂ����S�ƂȂ��ĂƂ�ǂ��s���Ă���B������A�Ƃ�ǂ��܂����́A�ǂ��\�����鐢�т����l���o�č�Ƃ�����B�����A�킪�Ƃ́A����L���s���ɏZ��ł���킽�����A���̒n��̎�����̍\�����ł͂Ȃ��B���������āA���̒n��ɏZ�ޏ]�o�ɗ��݁A���߂ĎQ���u���v�Ƃ��Ęm�������Ă����Ă��炤�B�u���N��A7�l�s������A���̑O�ɒu���Ƃ�m�������Ղ�����Ă����Ă��낧�Ă���v�Ə]�o�ɗ���ł������B
���[��6���ɉ�����B�킽�������́A�V��̍���Ă��ꂽ�݂�6�A����ʂɁA����������|�Ƃ̐�ɋ��݁A�n�܂�15���O�ɂƂ�ǂ̗����Ă���x�k�c�Ɍ��������B���v�Ԃ��Ȃ����ԂȂ̂Ŕ������肪�c���Ă����B
����������ł��~�肽����A���N�̔N�j�A�N���ɂ���āA�����܂���Ƃ�ǂɉ�����ꂽ�B�ŏ��͂���낿���Ƃ������A�����ɒe����悤�ȉ��𗧂ĂĂƂ�ǑS�̂��ށB����ƁA���Ɋ����グ��ꂽ�̕����܂��ɂ��Ɨ������Ă���B
���Ƃ�ǂ��Ă�����Ȃ��O�ɁA�Ƃ�ǂ��l������Œ肵�Ă����R���A�Ƃ�ǂ̉��A�G�̎}�Ȃǂ����炩���ߐςݏグ�Ă�����ɓ|���B����ƍ��x�́A���̕����̎R���R���オ��B�|�ꂽ�Ƃ�ǂ̍��g�݂̖Џ@�|���Ƃ��ǂ��傫���e����B�W�܂���90�l�قǂ̐l�����͂��炭�����ΐ����������Ɍ��Ă������A����܂�ƁA�����ŖݏĂ��n�߂��B
���킽�������̒|�Ƃ�3���[�g���قǁB���\�{���̊Ƃ̒��ň�Ԓ����B���̐�ɋ��݂��ɂ������ďĂ��̂����A���̒����ł���͉ɂ��Ԃ���B������A�ɂ��������܂܁A�Ƃ��痣��ďĂ��オ��̂�҂l�������B�������A�͋����̂ŁA�݂͏Ă��オ��܂łɏł��Ă��܂��B
���킽���͏ł��Ȃ��悤�ɖ݂����獂���������Ă��������B�����傫���Ȃ̂ł��̋����ŏ\�����Ǝv�������炾�B�Ă̒�A�݂͏ł��邱�ƂȂ��Ă��オ�肾�����B��̍���Ă��ꂽ�݂͒��a15�p�قǁB�Ă��オ�������͂��珇���A����Ă͐H�ׂ��B�������������āA���̂܂܂ł����������B�|�ŋ������͏Ă��c��B�����ŁA�݂̈ʒu��ς����ݒ����ďĂ��B�ŏ��͂ǂ�ǂ���ɉ^��ł����݂����A�r������ݖ��Ƃ��C�ۂƂ����~�����Ȃ�i�W�܂����l�̒��ɂ́A����Ȃ��̂�p�ӂ��Ă����l�������j�A�Ō�͌��ɉ������ނ悤�ɂ��ĐH�ׂ��B���܂��Ă����������ŁA�傫�Ȃ������܂�܂镠�ɂ���Ă��܂����̂ł���B�H�I���ƁA�݂��A���܂ŋl�܂����悤�ȋC�������B
���ݏĂ����n�܂�ƁA�����ӂ�܂��A�̎���̘b�����͂��������ɂ��₩�ɂȂ����B�����Ƃ킽���́A�L���s���܂ŎԂ��^�]���ċA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���������߂��Ă��A�A����肪�o��v����}���Ȃ��牽�x���f�����B��������A�S�����̂悤�ɗx��̂����A�Ǝv���Ȃ���B�Ƃ�����A�����Ƒ��́A�������҂�Ő���Ȗ�́u�ΗV�сv�ɖ��������l�q�������B
�u������������o��I�v
���Ƃ�ǂ��n�܂��Ă���ꎞ�Ԃ��܂肷��ƁA�킽�������͈����グ���B���̋x�k�c����Ԃ𒓎Ԃ��Ă��鉮�~�܂ł́A�����̖铹�ł���B����ƁA�����̖��������グ���B�u������������o�Ă�I�v����܂ł͂Ƃ�ǂ̉ɒ��ӂ�D���Ă������A���̉��痣���ƁA�ق̔������ɖڂ��������̂ł��낤�B���̎q�͕��S�������납�炸���ƍL���s���ɏZ��ł���B������A���i�͖������グ�邱�Ƃ͂Ȃ����낤���A���グ���Ƃ��Ă��A���̑����͊X�̓��ɏ�����A�ڂ���ƈÂ����邾���ł���B�Ƃ�ǂ̖�͔�����菭�������������o�Ă����B����ł��A���̋�ɂ͊X����肸���Ƃ�������̐����o�Ă����̂ł���B
�����̂Ƃ��A�ӂƁA���܂̐����ɂ͖邪�Ȃ��Ȃ��Ă���A�Ƃ����v���������B�l���Ă݂�A��ɂ����Ȃ���Ƃ�ǂɂ����A��̈ӎ��͊ɂȂ��Ă���B
����1��15���A�����̖�̉Ղ�
���Ƃ�ǂ͏������̍s���ł���B���Ƃ͋{���̍s���ł��������̂��A�ߐ��ɂȂ��đS���ɍL���������̂������ł���B������A�����ԁA�����1��15��������ɂ����Ȃ��Ă����s���ł���B����͌����܂ł��Ȃ��A�V���̓������̎n�߁i�������|�����|�j�Ƃ��鑾�A��i���m�ɂ́A���A���z��j�ł���B����ƁA15���̖�͖����ɂȂ�B�܂�A�Ƃ�ǂ͖����̖�ƌ��т��Ă������ƂɂȂ�B
�����܂ł����Ƃ�ǂ́A���ߏ���Ȃǂ��Ă����肷��̂ŁA�����̈�A�̍s���̒��߂�����̂悤�Ɏv���Ă���B�������Ƃ������̂��A�吳���ɔ�ׂ�ƁA�ǂ����A�₩���������܂��Ă������Ƃ����j���A���X������B�������A�������ɂ͖L����j���_�k�V��Ɋ֘A���Ă���s��������悤�ɁA�������͖{���͔_�k�ɂƂ��Ă̐����ł������悤�ł���B�Ђƌ��̋��Ƃ��ẮA����ɁA�N�̎n�߂Ƃ��ẮA�������ɁA�V����薞���̂ق���������₷���B�������A�茳���Ƃ炷�قǂ̓������Ȃ���������ɂ́A�����̖�̉��O�́A�j�Ղ̐���₩���ɂ݂��Ă������낤�B
�������ʼn߂������吳������A���x�͐l�тƂ͉��O�ł̐V�N�ɏo�čs���B���������A���̎R�̒[���疞�����o�肾��������A���̐l�������݂�|�Ƃ̐�ɋ���ŏW�܂�B�݂����̌����Ė�A�̂Ȃ��Ŕ��������яオ��B���炭���āA�Ƃ�ǂɉ��������B�Ԃ���������������т��ēV���ɂނ��ė����オ��B�q�ǂ���������Ăɑ吺�Ś������Ă�B�ΐ���������ƁA�l�тƂ͖݂��Ă��n�߂�B�����o������������̂��ƁA�l�тƂ́A�����ŏĂ����݂�H�ׂȂ���_�k�̈�N��\�j����B
����������ɂȂ�A����z��ɕς��i1873�N�A����6�N�j�ƁA�Ƃ�ǂ������ɂ����Ȃ���Ղ�ł���Ƃ̈ӎ��͏����Ă������ł��낤�B�������A���{�l�̐����̊�Ղ��_�k�ł��邩����A�܂��A�邪��������A�����肪�ق̔����Ƃ炷�����́A���Ƃَ͈��̗̈�ł��邩����A�Ƃ�ǂ͖�̉Ղ�ł���Ƃ̈ӎ��͏����Ȃ������ł��낤�B
���Ƃ��낪�A���ł́A�킽�������w���̂���A���������āA1960�N��ɁA�Ƃ�ǂ͂�������p�~�����B�����āA20�N�قnj�ɕ�������B���̊ԂɁA�Ƃ�ǂ͖�Ɛ藣����Ă��܂����B�ނ���A�����̐�������邪�����Ă��܂����B���z������̋��X�܂ŐZ�����Ă��܂����̂ł���B
����i���z���A��j�Ɣ_�k
������́A���̉^�s�ɂ��������Č���������A�[���ő��z�N�Ƃ̂�������鑾�z���A��ł���B��ɂ͓�\�l�ߋC���D�荞�܂�Ă���B��ł͐��m�ɂ͕�����Ȃ��A���z�̉^�s���������߂ł���B����̋N���ł��钆���́A���{���l�A�����X�[���n�тł���̂ŁA���z�̉^�s�ɂ��������Ďl�G���߂���B���������āA�ߋC�̖��̂́A�G�߂̕ω����������̂������Ă���B
�����A���z��瑾�z��ւ̈ڍs�́A���Ɩ�̋�ʂ��Ȃ����邱�Ƃł���B���z���1�N�z�N�i����t�����玟�̏t���ɂ�������ԁj�Ƃ��A1���ϑ��z���Ƃ���B���̌�����́A���A��̌���30���قǂł��邱�Ƃ��l����A���A��̖��c�͂��邪�A��{�I�ɂ͔C�ӂł���B�܂�A���̉^�s�Ɩ�̗̈�͗�쐬����r������āA���O�I�ȑ��z�̓����������ړx�ƂȂ�A���̌��ʁA���Ɩ�̐��������ʂ��������B
�����z��́A�����@���炢���A1�����ɕ�����莞�@�ł���B1����������24�̎��Ԃɕ������A���Ԃ͓���������60�̕��ɕ����Ƃ�������ł���B����ɑ��A�s�莞�@�́A���Ɩ�̊�{�P�ʂ͒������Ⴄ�B���{�ő��z��̗p�ȑO�Ɏg���Ă����s�莞�@�ł́A���Ɩ�����ꂼ��傫��6�ɕ�������B�����̎ړx�́A���z�̉^�s�ł���A���̉^�s�ł���B������A���Ɩ�̒����́A�܂��A���ꂼ��̎��Ԃ̊�{�P�ʂ́A�G�߂ɂ���ĕϓ�����B���̕s�莞�@�́A�V�̂̎��R�ȉ^�s�ɂ���đg�ݗ��Ă��鑾�A���z��ɂނ���e�����B
�����āA�P�������Ă����A���z��͋ߑ�^�s�s�ɑ����A���A���z��͔�ߑ�^�_���ɑ����Ă���B
���ߑ�I�Y�ƁA���Ȃ킿�A��K�͍H�Ƃ���ՂƂ��鏔�Y�Ƃ́A�����G�߂̋�ʂɔς킳��Ȃ��B1���Ԃłł��鐻�i�́A���ł����Ă���ł����Ă��A�^�Ăł������ł��A����1���Ԃłł���B�܂��A�ߑ�I�J���ɂ��Ă��A�莞���ɏ]���Ă���B1��8���Ԃ̘J���_������ׂA����8���Ԃ͒����G�߂ɂ���Ē������ϓ����邱�Ƃ͂Ȃ��B���܂��ܕϓ����Ȃ��A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�J���̋ߑ㐫�̖{���ɂ��������āA�ϓ����Ȃ��B�����Nj���ړI�Ɏ��Ԍ��߂ŘJ���͂�����J���_�莞����v������̂ł���B�܂�A�ߑ�^�s�s�ɂ͑��z����ӂ��킵���B
���Ƃ��낪�A��ߑ�i�O�ߑ�H�j�^�_���͑��A���z��I�ł���B��ǎd���͖��Z�Ɏn�܂��Z�ɏI���B��ɂ͂ł��Ȃ��B�܂��A���������Ȃ�ɂ�āA�ǂ�ǂ��̍앨���ǂ�ǂ��ɐ�������悤�ɂȂ�B����ɉ����āA��ǎd����������B���オ�莞�����Ƃ낤���Ƃ�܂����A�_�k�̎��Ԃ͖{���I�ɕs�莞���Ȃ̂ł���B����������A�_�k�̔ɊՂ̃��Y���ƒ���̒����̕ω��͑Ή����Ă���B������A���z�̗��O�I�^�s�ł͂Ȃ��A���̎��R�Ȗ��������ɂ��ƂÂ��A���ƂƂ��ɖ���ӎ������Ă���鋌��͔_�k�����ɂȂ��ށB
������͂���ɑ��z��̐��i�������Ă���B�����ȑ��A��ƈႢ�A���z��Ƃ̍����[���Œ������邱�ƈȊO�ɁA��ɂ͑��z�̉^�s�ɂ���ċ�����\�l�ߋC��������Ă���B��\�l�ߋC�ɂ͋G�߂̕ω����������̂������Ă���B�_�k������̒����̈Ⴂ�ɂ��������ĔɊՂ��J��Ԃ��Ƃ������Ƃ́A�����X�[���n�тɂ����ẮA�G�߂̕ω��ɉ����ĔɊՂ��J��Ԃ��Ƃ������Ƃł���B��\�l�ߋC�Ƃ́A������A���z�̉^�s�ɂ��ƂÂ��_�k��ł���A�_�k�̔ɊՂɒ���̕ω��Ƃ͕ʂ̊ϓ_����Ή����Ă���B
�������̐�������邪�����Ă��܂����A�Ƃ������Ƃ́A������A��@��́A�����ȑ��z��̗p���ꂽ�A�Ƃ������Ƃł���A���Y�������猾���A����̌��ƋG�߂̂߂���Ƃ������e���͂������Ȃ��Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B�Ɩ����Ƌ@��̕��y�����̌X���ɂ��������̔��Ԃ�������B
���Ƃ�ǂ�1960�N��ɂ�������p�~���ꂽ�̂́A���̎���Ɂu���z��v�I�Ȑ������悤�₭���{�̑命���̐l�̖ڕW�ƂȂ�������ł���B�܂��A���������Ƃ�ǂ���Ɛ藣����Ă��܂����̂́A���̐��������ɂ����̐����̊�ɂȂ�������ł���B
�����̍��́A�Ƃ�ǂɌ��炸�A���x�������ɂ�������Ǝ̂Ă�ꂽ�l�X�ȍs������������Ă���B�����āA�����̍s���̓}�X���f�B�A�ŏЉ��A���݂̐����Ŏ���ꂽ���������߂��Ă���邩�̂悤�Ȉ�ۂ�^����B���s����g���A���㐶���̂Ђ��݂��u�����v�Ă����u�X���[�v�ȍs���ł��邩�̂悤�Ɏv�����肷��B
���������A���܂̂Ƃ�ǂ̖�́A����1��15���̖����̖�ł͂Ȃ��B�Ƃ�ǂ���ɂ����Ȃ���̂́A�ɘ_����A���܂��܂ł����Ȃ��B���������͖���Ă��Ȃ��B��Ƃ͏Ɩ����ɏƂ炳�ꂽ���̂��Ƃł���B�ނ���A����ɂ́A���z�ɏƂ炳�ꂽ�A�����ɂ́A�d���ɏƂ炳�ꂽ�A�������܂������������Ԃ����邾���ł���B���z��̐������u�����v�����߂�����̂�����ɂ��Ă��A���z��̏�ɕ������ꂽ�`���ł͂Ȃ��B
�����ɔR���オ��Ƃ�ǂ́A������A����Â����F�[���������ɏĂ��s�������A�����ꂽ��������ɐ������Ȃ����A����Ȗ₢�������ɈÎ����鉊�ł��낤�B