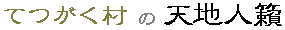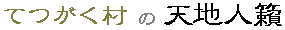☆ 2005-10-17 ☆ 秋の夜寒の月明かり
《籾を蔵に収めると、農耕の季節は終盤を迎える。その日は十四夜の月。月明かりのもと、従姉の昔話を聞いた。》
- 米を蔵に収める;- 月明かりの稲運び
米を蔵に収める
10月16日の日曜日は、雨の前日とは違い、さわやかな秋晴れだった。木曜日に刈り取り、乾燥してもらった米を、委託した人の家に取りに行った。
米は土蔵に入れる。午前中は、雨を吸った地面からのぼる水蒸気のため空気が湿っぽかったので、午後、土蔵を開けた。新米を収めるため、米の収納庫から去年収穫した米の残りを出した。米は籾のまま保存し、一月に一度、食べるだけ農協の精米所で籾摺りと精米をする。その仕事は妹に任せているので、米の残量は念頭になかった。残っているのは14袋であるから、少々多すぎる。一袋を精米すると、よく挽けて、1斗5升になる(1斗は15kg)から、2石(20斗)ほど残っていることになろうか。新米が十分に収穫できているのに古米を食べる気はしない。だから、なんとか捌け口を探さなければならない。今後は、定期的な買い手を探すなりして、計画的に消費しようと思う。
ウルチの収量は、籾袋の数にして38。去年より収穫は多いはずである(調べたところ、去年の記録は残っていない…)。軽トラックで2往復して運んだ。涼しくなった最近だが、収納庫に重い籾袋を積み上げる作業をすると、さすがに汗が流れる。
毎年のことだが、米を蔵に収めると、やっと農耕の一年が終わり、さらに一年の命が保証されたという安堵が身体に広がる。
この日は、久しぶりにのんびりと作業をした。来秋まで保管するコンバインの掃除、夏中草が生えるがままにしていおいたが、11月終わりにはタマネギを定植する予定の畝の草刈り、イノシシ防除のための電気柵(ただしダミー)の延長、キュウリなどに使った支柱の整理など、忙しいときにはなかなかできない作業を急かされる気持ちなしに片づけた。
月明かりの稲運び
日が落ち、東の空から十四夜の月が昇りはじめた。隣の畑で作業をしていた従姉が少し離れた私に向かって話しかけた。「こんな月が明るい夜に、稲を運びょぉった。」思い出した昔を自分で確認する独り言のようでもあった。その言葉に続きはなかった。ふとゆかしい気持ちになり、私は従姉のところに行き、話の続きを聞いた。
「昔は祭りの前に(当時、祭りは10月20日ごろだった)稲刈りは終えた。稲は稲架に掛けた。ゴウ[田圃のあるあたりをそう呼ぶ]でこぐ[脱穀する]こともあったが、家まで運んで帰ってこぎょぉった。こぐまでは、稲は縁側に積んじょった。ほいじゃけん、雨が続くような年には、いつまでも稲が縁側にあって家の中が暗かった。こいでから、籾を庭中に広げた筵で干しょぉった。」
今では刈り取った稲は完全に乾くまで稲架にかけておくが、戦後のある時期までは、稲架で大まかに乾かし、それから脱穀し、さらに籾を筵の上に広げて十分に乾かしていたそうである。父からもそんな話を聞いたことがある。「稲架で[完全に乾くまで]乾かすようになった頃には、大丈夫かの[本当に乾くのだろうか]と心配じゃった」と父は話していた。
従姉は話を続けた。「昔は子どもも働きょぉった。稲を背負子に負おて、月が出た晩にも運びょぉった。そしたら、ざっざっざと後ろで音がした。」稲はまだ籾がついている。歩く振動でその籾が鳴るのである。「その時期は、はあ[もう]寒かった。」
もう50年以上も前の話である。歳を計算してみると、彼女は小学校の高学年だったろうか。戦争末期、市街地から疎開し、藁屋根であった我が家に住んでいた。
今よりも気温が低く、また、今のように街灯が灯っていたわけではない。車も滅多に走ることはなかった当時は、日が暮れるとひと気のある音はほとんど耳に入らなかったろう。田圃から家に通じる道は馬車が通れるくらいの小道であった。月明かりの注ぐ、しんとしたその道を小学生の彼女が家に急ぐ。小さな身体に稲の重みが肩からのしかかり、耳には籾のざわめきだけが聞こえた。
「月が明るいと、あの頃を思い出すんよ。」彼女は他の思い出話もした。しばらく話を聞く間にあたりはすっかり夜になっていた。
まさしく秋の日は釣瓶落とし。帰り支度をして車に乗り込んだときは、まだ6時半であった。
|