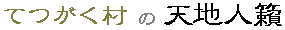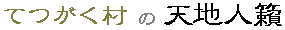11月下旬の夕方、私は帰宅途中、畑に寄った。隣家の前を通るとき、車窓から、その家の主人が堆肥らしきものを積んでいるのが見えた。隣には、その家の分家のおばあさんがいた。最初は堆肥だと思ったが、どうも様子が違う。家の主人がうずたかく積まれたゴミの山のようなものの上に載せているのは、土であった。もしかしたら焼け土!と私は心の中で叫んだ。
父の焼け土
父は焼け土をよくしていた。畑で抜いた草がたまってくると、まず枯れ木を積み、その上に枯れた草を重ねて、火をつけた。火が勢いを増してくると、さらに半乾きやまだ青い草を積んだ。すると火は一気に燃え上がらず、煙を立てながらゆっくりと燃えた。夕方になると、まだくすぶるように燃えている塊のてっぺんにトタン板を載せ、その板を大きな石で固定した。夜間に風が吹いて火が飛ばないようにするためである。翌朝になっても煙が出ていることがあった。燃え尽きると、あとには炭、灰、草の根についていた土、半焼けの草が残った。そしてそれを畑に戻した。
半焼けの草は種がついているのもあった。草の種は焼いて発芽不能にしたい。私が、焼け残った種は畑で発芽するのではないか、と心配したところ、父は、煙が通れば種は死ぬ、と言った。堆肥の発酵熱でも草の種は発芽不能になるそうだから、煙が通るほど火の近くにあった種もやはり発芽しなくなるのだろう。
焼け土をするために、父は剪定くずなどをとっておいた。屋敷の片すみには、木の枝の束がいくつもおいてあった。
昔はもっと大がかりな焼け土をしていた、と父は言った。山から木を切ってきて燃やし、その上に土をかけたそうである。焼けた土は肥料として使った。しかし、私はそのような焼け土を一度も見たことはなかった。推測するに、父のやっていた焼け土はミニサイズの焼け土、ないしは焼け土もどきであったろう。だから、本格的な焼け土のやり方を知りたいという思いが心の中に消えずにあった。
父は、死ぬ前に半年ほど入院していた。病が重くなり、病床に付き添うようになった時、焼け土の仕方を尋ねたことがあった。父は「いま頃、そがいなことをしょうったら、人が笑う」と言葉を返した。自分の病苦も一緒に払うかのような口調だったので、私は黙った。結局、父から焼け土のことを聞くことはなかった。
父の死後、私は父をまねて焼け土をした。しかし、火を土で蓋をして、文字通りの焼け土をすることはなかった。一度も見たことがないものは、そして特に必要がないのであれば、やろうという気はおきなかった。
焼け土の実際
隣家の主人が焼け土を準備している様子を見かけた私は、車を屋敷に駐車してから、デジタルカメラをもって隣家に向かった。「焼け土をするんや」と私は主人に声をかけた。八十歳に手が届こうか、という年齢である。九十をこえた分家のおばあさんは、主人が最後の土をかけて準備を終えるのを見ていた。
「庭の[剪定した]木を燃やしちゃろう思ての。半乾きのもある。それを並べて、ゴミを重ねたんよ。」見ると、灯籠[安芸地方では、盆に竹作りの灯籠を墓に供える習慣がある]の真竹も重ねてある。「土は、トラクターを洗った後に残った土をもってきたんじゃがの。一回洗う時にゃ、[土は]ちいと[ちょっと]じゃが、[長い間には]結構たまるもんじゃの。」土を運んだ一輪車が近くにあった。円錐形にうずたかく積まれた薪の周りを、解体した段ボール箱がぐるりと囲んでいた。「火を回しちゃろう思うての。」主人が火をつけた紙屑で薪の何カ所かに点火すると、火は枯れ草と段ボール箱を伝わって全体に回った。
薪が燃えるのを見ながら、主人とおばあさんは焼け土にまつわる話をはじめた。「○○のおじさんは焼け土がうまかった」とおばあさんが思い出し話をした。「焼け土をすると、ええがいに[いい具合に]土がずって来よぉった。」薪の上に載せた土が、薪が燃えるにしたがってずり落ちて全体を覆い、円錐形の土の塊ができる、ということである。すると、主人は口を挟んだ、「土がええがいに落ちるように、最初から木を組んどくんじゃけん。」
おばあさんは話を続けた、「土がずってきたら二三カ所、穴を開けんさった。ほしたら火か消えずにずぅっと燃える。」私は「その穴に煙突でもつけるんや」と訊いた。「煙突なんかつきゃせん。穴を開けるだけじゃ。ほしたら火は消やぁせん」とおばあさん。すると主人は補足した、「スクモ[もみ殻]を焼くじゃろうが。あれと同じよ。」スクモはいったん火がつくと燃え上がるでもなく、煙を出しながらゆっくりと燃えて、炭のようになる。
「○○のおじさんは、山の入り口の道の周りの木を切ってきて、それで焼け土をしよんさった。青い木があるとなごう[長く]燃える。」その山はいまは原野になっている。昭和四十年代はじめに村を挙げて葡萄園を開設し、失敗した後、放置されたままになっているからである。かつては共有地と私有地とが混在した山林であり、里山として利用されていた。葡萄園のために里山の木が伐採された頃は、次第に焼け土などはされなくなった頃に重なるように思われる。
昔の肥料事情
話は昔の肥料事情に移った。
「焼け土は肥料にした。タネ屋のおっさんが、『人参は焼け土がありゃぁ、それだけでできるんでがんすで』言よぉた。タネ屋が言んじゃけん、まあ嘘じゃなかろう。焼け土にゃ、カリがあるけん、ええんかのぉ。」と主人が話した。おばあさんは、「○○のおじさんは『土は煙が通るだけでも、ええんでがんす』言ょりんさった」と言い加えた。煙が通るだけでも草の種は死んでしまう、と言った父の言葉を思い出したが、さらに、煙の中にふくまれる肥料成分が土に多少なりとも付着するのだろうか、とも思った。私は「根のものにはなんでも効くんじゃないかね。ジャガイモでもええんじゃない?」と補足した。
「うん。ともかく昔ゃ肥料がなかったけん、焼け土でもなんでも肥料にした。」主人は、終戦直後の物資が不足していた時代の話をはじめた。「呉の街に下肥をもらいに行きょうた。街に入るあたりで、よお村のもんに会よぉった。」
呉の市街地は、村から徒歩で峠ひとつを越えて一時間あまりである。峠を越えると眼下に市街地と瀬戸内海を見ながら、灰ヶ峰の急峻な斜面を下る。いかに急峻であるかは、灰ヶ峰が天然の要害になり、明治はじめに呉に軍港が開かれたことから、想像していただけるだろう。遠路、下肥をもらいにいくのだから、肥たごを担いででは無理であり、牛に肥たごを載せた車を引かせた。きつい坂を降り登りする行程のため、暑い時期には牛の疲労を防ぐために朝早く出かけ、日が高くならないうちに戻った。
私は話を聞きながら状況はひたすら想像するしかなかった。ただ、ひとだけ、状況を具体的に想像する手がかりが記憶にあった。二十年ほど前だったか、終戦直後の呉に駐留したオーストリア軍の一兵士が撮った写真展が、開催されたことがあった。何枚もの写真の中に、灰ヶ峰を登る七曲がりの坂道で撮られた農夫の写真があった。飛行兵がかぶるような帽子を頭に、すくっと立った壮年の男が、精悍そうな顔をカメラに向けていた。彼の横には車に載せられた肥たごが写っていた。写真には男の名前は不詳となっていたが、後日談に、その農夫が村の人であることが分かった、と聞いた。自分の父であると確認した女性は、その写真の前で涙した、という。私は主人の話を聞きながら、その写真を思い出していた。
下肥は農作物との物々交換で分けてもらった。「葉物をもっていくと、[下肥は]なあ、言やがる。米や大根を出しゃ、くれる。ほいじゃが、田舎でもろくに米を食えん時代じゃけん、そうそう米はもって行けんよの。」主人は遠い過去を笑いながら語った。「自分がたの下肥だけじゃ足らんで、自分がたのがのうなりゃ[なくなれば]呉にまでもらいに行きょぉった。焼け土も肥料にしよぉった。」
焼け土の再現
父が語った昔の本格的な焼け土を彷彿とさせる現場を見た私は、記憶の鮮明なうちに自分でもやってみようと思った。
十二月半ば、私は畑や屋敷のあちこちから木切れや枯れ草を集めてきた。この頃は焼け土もどきも滅多にしなくなったので、材料はすぐに集まった。
土はトラクターを洗った水を流し込む溝から掻きだしてきた。トラクターや耕耘機で耕耘し田圃や畑から出る前に、ロータリの刃、ロータリーカバーの裏、タイヤの凹部に付着している土をそぎおとす。土のついたまま圃場から出る人もいる。すると、トラクターの走ったあと農道にはあちこちに土の塊が残る。しかし私にはそれができない。土あってこその畑であり、田圃である。土を粗末にする者は百姓ではない、という気持ちが私にはある。だから、機械についた土は圃場に戻す。しかし、完全にそぎおとすことはできない。残った土は、機械を洗うときに水とともに流れる。そこで、機械を洗う場所には水が流れ込むように溝を掘り、溝の下端では石で水を堰き止め、土を溜める。一シーズン流しこんだ溝には、溝が埋まるくらいに土が溜まっていた。その土を運んできた。
土は焼け土に十分な量はなかった。今回は見聞を自分の体に覚えさせる経験であったので、足りない土は、畑で抜いては積み、半ば堆肥化した草で代用することにした。
燃え上がった薪はしばらくするとバランスを崩して、載せた土が一方向に滑り落ちた。薪の積み方、土の載せ方、載せる土の量、火の回し方、すべてが素人技のため、焼け土はしょっぱなからつまずいた。あわててスコップや鋤簾で土を戻し、さらに堆肥化した草を積み加えた。しばらくするとなんとか焼け土らしくなった。燃え上がった塊は次第に縮み、土と草が全体を大まかに覆った。炎はたたなくなっても塊の中では適度に酸素補給をたたれた(言い換えれば、ゆっくりと燃える程度には酸素を補給されている)木が燃えていた。一時間ほどして、一輪車の古い荷台を使って蓋をした。次の日、丸一日経った焼け土はまだかすかに煙をあげていた。
今では老齢の人たちだけが記憶している焼け土。その焼け土をたまたま再現しえたのは、永遠に失われたかと思われた何か大切なものを発見したかのように、心踊る体験であった。この焼け土を畑に戻してやると、畑もまた何かを思い出すだろうか。