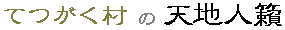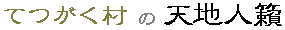□4月5日朝、ひとりで山を歩いた。山の境界を確認するためである。
□先週の日曜日、共有林の境を確認するために地権者たちが揃って山歩きをした。わたしも地権者のひとりである。わたしはまた、共有林と境を接する山の地権者でもある。境を接するわが家の山は二カ所あるが、いずれも面積は狭い。山の境は尾根とか、石とか、枝が切り落とされた木とかが目印である。境を決するものは、ほかには談合図と呼ばれる大雑把な図面しか存在しないから、結局のところ地権者の記憶がたよりである。1週間前の確認では、わたしには納得できないところがあったから、その箇所を再確認しておくために、再度ひとりで山歩きをしたのである。
□わたしは共有林の周囲をぐるりと回った。
□昔の人は生活の必要上、よく山に入った。わたし自身の小さいころの記憶からだけでも山に入って、燃料にする木、焚きつけにするためのモク[枯れた落ちた松葉]、堆肥にするための落ち葉などを集めた。秋になれば、松茸など茸も採った。家を建てるときには、自分の山から木を伐りだしたりもした。いま問題になっている山に入ると、小学生に上がるまえとか、小学生低学年のころとかの記憶が甦える。たきぎにするためだろう、柴を集めては蔓で縛っている父母の横で、刀にみたてた棒を振り回しているわたしとか、父と一緒に山道を歩きながら境を教えてもらっているわたしとかが、記憶の底から甦えってくる。しかし、いまでは山に入ることはほとんどない。木の代わりに、化石燃料や電気を使う。肥料は化学肥料か有機肥料にしても金肥である。家を建てるにしても、自分の家の山から木を伐りだしたのでは、かえって高くつく。山にはよく来て年に一度である。かつては境のしるしであった獣道や柴を運び出す馬が通った小道は消えてしまっている。その結果、いまでは境が分からなくなったという話もよく聞く。
□だから、わたしにとって山の境を記憶するとは、生活の必要上というよりは、いまのわたしに結晶している自分の歴史を大事にすることである。自分の歴史に結晶している祖たちの歴史、さらにかれらの歴史が同じ村に生きた他の人びとの歴史と交わった共同的な歴史を忘れないためである。逆に、境が分からなくなったり、境を変えられたりすることは、自分自身の一部を見失うことであり、自分の歴史を否定されることである。わたしがいまはなんの「価値」もなくなった山の境に執着し、1週間ほどのうちに3度も(共有林の境を確認した翌日にも山に入った)境を確認したのは、そのような、いわば実存論的な動機もある。
□わが家の山との境を確かめ、また他家の山と共有林とで境が争われている箇所の尾根線を確かめたりしながら共有林を一周して、わたしは山から舗装道に出た。すると、横道から荷台に木製の梯子をつんだ軽トラックが上ってきて、わたしを認めると止まり、運転していた人が出てきた。相手はわたしを分かっているようだったが、わたしの方はその人が誰か分からなかった(最後に尋ねて、小中学校のときの同級生のお兄さんであることが分かった)。その人はわが家の山の隣に山をもっている。いまは舗装道がついて変わってしまった昔の地形についてその人は話した。
□「大積道[大積という地名の集落に向かう道]から坂を上がっていく山道があった。その道の右側は[大積道に下る斜面となり]ハゲじゃった。山道を新池の方へちょっと行ったら、こう左右に道があったわいの。」どうも山道と直交する道のようである。
□その人の話を聞くと、いまは共有林の一部分とみなされているが、わたし自身はわが家の山の一部だと認識している場所が、やはりわが家のものではないかとの認識を深めた。その人は、「あの大けぇ松はあんたがたんじゃなぁんや」と枯れた大きな松の木を示して言った。その松の木がわが家の山に生えているものかどうかはたしかではないが、そのあたりを共有林とわが家の山を区切る獣道が走っていた、という話を別の人からも聞いた。いまは獣道はないが、その幻の獣道と舗装道をはさむ、直角三角形の形をした狭い部分が、過去の暗がりから浮かび出てくるかもしれない私の歴史である。思い起こせば、小さいわたしと一緒に歩いていた父が道路から少し上の方を指さしながら「あの辺までが、うちの山じゃ」と教えてくれたのが、その部分のように思える。そして、死ぬ2年ほど前に、境確認のためわたしと二人で山歩きした父が「こっち側にもうちの山が残っちょる」と教えてくれたのが、その部分である。
□しばらく周辺の山の境や所有者、いまは舗装道ができたため廃道になった大積道の位置などについて話し合ったあとで、その人は「うちも[子どもに]境を教えとかんゃいけんのぉ」と言いながら、車に乗って走り去った。
□山にはあちこちにこぶしの花が咲いていた。春の朝の湿った空気のなかを、はらりと落ちてくる花弁もあった。こぶしの花はすぐに散ってしまう。桜にしろこぶしにしろ春の花は散りやすい。それは、春の勢いを象徴しているように思える。春になったかと思うと秋に向かって命が全速力で走り始める、その勢いである。この朝、地中から湧き出る命の、束の間の化身かと見えるこぶしの勢いに促されて、私の記憶の薄暗がりからも歴史の一部が明るみに出てきたようであった。